June 2013
現地に大きなインパクトを
残そうなんて思ってない。
我々が目指しているのは、
これから広がっていく
モデル作りなんです。

特定非営利活動法人 シャプラニール
国内活動グループ・チーフ
小松豊明様
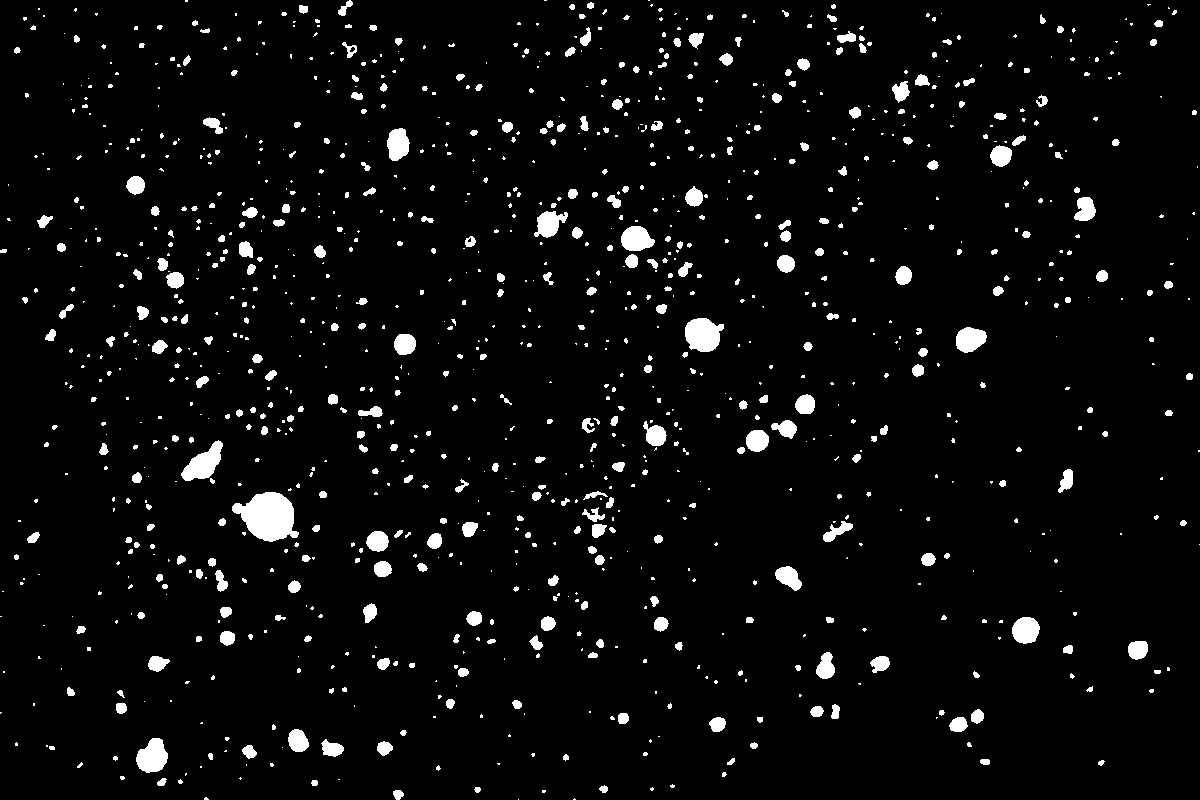
みんなの
"知りたい"を、
叶えたい。
This month's interview
まずは小松さん個人のことについてお伺いしたいのですが、
国内活動のチーフということで、普段はどのようなお仕事をされていますか?
国内活動には大きく分けて3つあります。ひとつは、資金調達です。継続的に寄付をしてくださる会員が今3000人くらいいるので、更新などの手続きをしています。それからステナイ生活も、資金調達の活動の一環の、物品寄付という形でやっています。
ふたつ目は、広報や渉外、いわゆる企業との付き合いですね。それからもうひとつは、お金に関係しないところの国内活動。例えば講演会とか、スタディツアーを実施したりだとか、色んなイベントをやったりだとか、あとは開発教育の教材を作ったりという、お金にはならないけれど、シャプラニールの活動あるいは海外教育の考え方を広めていくための取り組みですね。こういったもの、要は日本国内で行われることを全般的に管轄しています。
それとは別に、震災の対応ということで2011年の3月から福島でずっと活動をしていて、その責任者も兼任しています。
ちなみに震災の前は、フェアトレードを担当していました。その前はネパールの事務所に駐在員として行っていた時期もあります。今、シャプラニールに入って13年目になります。
NGOに入ろうと思ったきっかけはありますか?
NGOに入りたいと強く思っていたわけではないんですけれど、国際協力とか国際交流とか、とにかく国際なんとかっていう名前のつくような仕事をしたいな、と漠然と思っていて。でも具体的な経験も実際ないし、どうしようかなぁと思っていて、地元北海道の函館にある北海道国際協力センターという財団法人に入ったんです。そこで5年ほど仕事をしていた中で、JICAの研修で日本に来ている人たちに技術研修のプログラムをやるような機会があって、どちらかというと国際協力の方にだんだん興味をもつようになったんです。自分も外に出て国際協力の活動をしたいなと思ってきて。ただ私も大学で勉強した訳ではないし、1回勉強した方が良いと思って、そこを辞めて東京の大学院に行って開発経済の勉強をして、修士の2年間が終わってからシャプラニールに入りました。
現地での協力者の見つけ方で気を付けていることはありますか?
例えば私が駐在していたネパールは、昔から政府の方針として現地でのパートナーNGOをもつことが決められているので、現地での活動はパートナー探しから始まるんです。気を付けていることというのは、ひとつは活動の目的を共有できているかどうかですね。
それから、団体の組織体制がしっかりしているかどうか。お金の流れがしっかりしているかですね。
あとは面白い活動ができるかどうかかなぁ。発展的なものになっていかないとつまらないんでね。この人たちとだったら面白いことができそうだなって、要はアイディアをもっていたりだとか、新しいもの、本当に意味のあるものを作っていこうという意識があるか、を重視して考えますね。パートナー探しと同時に、現地にどういう問題があって、どういう活動をすべきかを明確化していきます。そのために、最初はまず調査をします。例えば児童労働の問題を解決するために、どこにどんな問題があるのかを把握しようと、ストリートチルドレンに話を聞いたりします。それにまず数ヶ月〜1年の時間をかけます。様々な状況で働いている子供達がいて、彼らがなぜそのような状況になっているのか、またどのような問題を抱えているのか。そういうことを調査の中から読み取って、我々としてはここにアプローチしていこう、そのためにどういう団体と一緒にやったらいいのかということを考え、パートナーの団体を決めていきます。
調査についてなのですが、自分たちが聞きたい情報をうまく引き出す方法はありますか?
それはたぶん、我々でも直接はできないと思いますね。調査活動についての手法を勉強はするんですけれど、日本人が村に入って行って聞き取りをするというのは、非常に難しい。我々だけでは無理ですね。必ず現地の人たちと一緒にやります。さっき言った児童労働の調査にしても、調査のためのパートナーをまず探して、そこと一緒にやります。調査の手法とか、誰と一緒にやるかは一緒に相談して決めて行くんですけれど、実際に通りへ出てって、働いている子供たちに話を聞くのは、現地の人にやってもらわなければならない。例えば、ネパールで子供捕まえて英語で話しかけたって通じない。私なんかネパール語はできますけど、私がネパール語で話しかけたって、答えは返って来るけど、それが本当かどうかなんてまったくわからないし、判断しようが無いですよね。言葉の細かいニュアンスなんかもわからないしね。特にストリートチルドレンなんかは独自の言葉を持ってたりするのでね。日本の若者だってそうじゃないですか、大人からしてみれば何を喋ってるんだか、さっぱりわからない。それと一緒ですね。でも、まったくやらないわけじゃないですよ。我々の方が逆に現地の人が持ってない視点で質問を投げかけたりとか、できることはあるんで、一緒にやるんです。日本人だけでも現地の人だけでも、本当に意味のある調査は難しいですね。
プロジェクトを立てる時も、現地NGOと住民とシャプラニールが一緒に作っていくのですか?
そうですね。開発の流れとしては、参加型ということが常に言われています。我々支援する側が勝手に調査して勝手にプロジェクトを立てて勝手に進めて行くということはまったくナンセンスであって、住民の声がきちんと反映されている、もっと言えば住民が直接行動できるようなプロセスにしていかないと。プロジェクトを作るプロセスの中に住民がきちんと参加していて、自分たちの問題は何なのか、それはなぜなのか、それを解決するために何が必要なのか、何をしなきゃならないのか、ということを住民自身が考えていかなければならないんです。そういうプロセスを経ることによって、プロジェクトが終わった後も住民達が自分でその活動を続けていく可能性が生まれていくことにもなります。
現地の人たちの問題をどうにかしたいと思うのだけれど、住民との間に問題意識の差を感じるときに、どうしていますか?
常に意識しているのは、我々が、これがいいだろう、こうすべきだ、と思って相手の話も聞かずにやると、まず失敗するということです。例えばトイレのない村があって、衛生環境が悪いということに我々の間でなり、トイレットリングをつくって簡易トイレを作ったんです。半年後に行ってみると、そのトイレットリングがそのまま置いてあるんですね。相手はとりあえずもらっておこうくらいの気持ちで受け取って、面倒くさいから放ってある。そんなようなことは、本当によくあります。彼らが何を問題と感じていて、どうしたいのかというところが一番の鍵になると思います。問題は確実にあるんだけれども、住民はそれを問題として感じていない。そういう時、それは本当に問題としなくて良いことなのか、それともやっぱりそれは問題としなきゃまずいことなのか。それはやっぱり、我々が見極めなくちゃいけない。そして後者の場合、本当は問題があって解決しなきゃいけないんだけど、住民が気付いていなかったり、自分たちの問題として捉えられていなかったりする時は、そこの気付きを促すことですね。意識化っていう言葉がありますけれども、自分たちの問題を、自分たちの問題として気付く、そしてその解決のために何とかしようと動き出す。そこのプロセスのお手伝いを我々がすることだと思います。相手が問題だと思っていない状況で、それでもこっちが、これは問題なんだから!ってやっちゃうと、やっぱりうまくいかないと思いますね。住民自身が動かなきゃならない。それが何よりも大切なんだと思います。
住民に問題を気づかせる方法としては、直接話していくしかないのでしょうか?
ただ漠然と、あなた達気付きなさいよ、と言ってもそんなことできません。例えば参加型農村開発手法(PRA手法)というのがあります。住民参加型で調査をするんですけど、調査をして現状を知ることが本来の目的じゃない。本当の目的は、住民自身が自分たちの問題に気付くことなんです。それで、何とかしなきゃという行動に結びつけていく。参加型農村開発手法というのはそのための調査手法で、住民がどう考えてどう行動するのか、そこを促していくというツールですね。例えば村の歴史を聞いたりだとか、地図を作って、村の中のリソースを確認する。その中で、自分の役に立つものに気付いていく。あとは、農作業においてのシーズナルカレンダーを作っていくとかね。何月に何が採れるとか、干ばつの危険、自分たちが忙しい時期に気付いたりする。大事なのは、調査を通してとか、何でも良いんだけど、自分たちで気付く、ということです。外から入ってきた私たちがぱっと見て把握できることって本当に限られているんですね。我々自身も、聞かなきゃわからないわけですよ。私たちが、問題点はここだなって思っても、違う立場の人に話を聞いたら違う事実が出てきたりする。住民自身がどうしたいのか考えて自分たちで動いて行く、そのプロセスの全体を見てアドバイスする、そういう役割が、我々のできることなんですね。あくまで我々がやることはサポートなんです。
最終的には現地の人たちが自分たちでプロジェクトを運営していけるようにする、ということですが、撤退のラインの様なものはありますか?
プロジェクトを始める前に、必ず計画を立てます。まずは調査して、プロジェクトを立案する中で、どこにどんな問題があって誰が対象で、何をしなきゃならないのか、どのくらいの活動の規模になるのかを考えて、それはどのくらいの時間をかけてやるのか、調査からわかった事実をもとに積み上げていきます。そこから目標に向かって逆算して、いつ何をやるのかの計画を立てるんです。そして、その計画に基づいてやっていって、予想より早く進む場合も時間がかかる場合もあるのですが、その時々で対応していきます。目標を達成できた時点で終了、というわけです。撤退した後も、たまに訪れて状況を確認したりすることはしますね。
学生団体の欠点として、長期計画を立てたとしても、立てたメンバーが卒業していってしまう。また、仕事として行っているNGOとは活動のレベルも違えば、駐在することもできない。そこに、学生団体としての活動の難しさを感じるのですが。
あんまり我々みたいな、仕事として、プロとして活動している団体を参考にして、真似しようとは思わないほうが良いんじゃないかな。学生の援助なら、学生の援助なりにできることがあるんじゃないかな。結局、そんなに大きなインパクトを現地に残すというのは、我々もそうなんだけど、できないんですよ。我々の仕事というのは、そんなに大きな規模のものではないんです。我々が意識しているのは、モデル作りなんです。小さいプロジェクトなんだけど、こういう風にうまくいきました、というモデルを作って、それが色んな所で真似されて広がっていくということができればな、と思います。何か小さいことなんだけど、こんな面白い取り組みをやってみたら、うまくいきました、とかね、そういうようなものがひとつでもできればね、現地にもインパクトがあるし、日本の社会にもインパクトがある。あ、学生がこんなことできるんだって。そしたら他の人たちもね、自分たちもこんな風にやってみようか、という広がりがあるかもしれない。学生なんだから、プロフェッショナルになろうと気を張らずに、面白いことをやったら良いと思います。
今までの駐在経験の中で、一番心に残っていることは何ですか。
いろんなことを思い出しますけれど、そうですね、印象に残っているのが、ストリートチルドレンの支援活動のために元ストリートチルドレンの青年たちが立ち上げた若者グループがあったんです。すごくやる気のある青年たちで、自分たちの後輩が自分たちと同じような、辛い目に合わないようにしてあげたいという思いをもっていました。私たちも協力して、元ストリートチルドレンが今のストリートチルドレンの面倒をみるという施設を作ったんです。子供たちが寝泊まりもできて、ご飯も食べられる家を、土地を借りて住宅地の中に建ました。でも、周りの人から文句を言われたんです。要はストリートチルドレンって、世間からすると白い目で見られる存在なので、野良犬と変わらんみたいに扱われて。そういう子供たちのたまり場みたいなのができるということで周りの住民はやっぱり文句を言うわけですよね。それで一回、その地域の自治会長さんとその地域の有力者と何人か来てもらって、私がお話をしたんですね。「ストリートチルドレンにはこういう問題があって、ただもちろん、すぐ子供たちが突然更生できるわけじゃない。
それでも少しずつ状況を良くしていきたいんだ。」っていうことを話しているうちに涙が出ていて。そのせいかどうか分からないけど、集まった人たちも話を聞いてくれて、その後は文句を言う人の数も減っていったんです。そしてそれと合わせて、ストリートチルドレンたちが、このままじゃいけないって、清掃活動を始めたんですよ。自分たちがただ集まって恩恵を受けるだけじゃいけないって、自分たちの施設の敷地だけじゃなくてその周りの地域全体のごみ拾いをするんです。ネパールってね、みんなすぐごみを捨てちゃうんですよ。基本的には捨てたら捨てっぱなしなので汚い。でも、子供たちが掃除を始めたら周りの住民もそれを見て、自分たちもやんなきゃなんないんじゃないだろうかって思って出てきてね、一緒に掃除を手伝ってくれたんです。それでだいぶ周囲との関係性ができて、それ以降はそんなにしょっちゅう怒られることもなくなりましたね。私がやれって言ったわけじゃなく、子供たちが自主的に動いてくれて、それが周辺住民との関係の改善に繋がっていったのが嬉しかった。それが、印象深い思い出ですね。
あとは危険な目にあったことも、もちろんありました。
さまざまな危険と隣り合わせのなかで、住民の方たちとの経験が小松様の原動力となっているのですか?
そうですね。私は、命を落としてまで活動を続ける必要はないと思っています。命を懸けて、自分が死んでもこの活動を続けるんだっていう必要は全くないと思っていて、だって私にも家族がいるし、その、誰かの命を犠牲にしてまでやらなきゃならないことってないと思っています。ただ、そのどうしても日本の事務所でパソコンに向かっているのとは違って、危険性というのは多少出てくるので、あとはどういう危険があって、どういう対応が必要なのか、何か起こった時にどうすればいいのか、っていうのは常に準備しておかないといけないし、それがないとやっちゃいけない。そして、そういう危険があってもやらなきゃいけないと思うのは、やっぱり誰かの役に立ってる実感があるからだと思います。
NGOに入って活動して、前と心境的に変わったことってありますか?
ありますね。特に現地で駐在して学んだことっていっぱいありますよね。我々は海外協力で支援する・されるでいうとする側なんですけど、結局そこから我々自身が学ぶということもたくさんあります。
例えばコミュニティーの役割。日本、特に都会だとね、コミュニティーのつながりっていうのはほとんど失われていますよね。
でも現地に行くと、家族とか親戚とか地域の人同士の繋がりが本当に濃いじゃないですか。話してると、あぁそこの何とかさんねってみんなが知ってて、必ずどこかで繋がってる。大変な状況にいる人でも、誰か助けてくれる人が周りにいる。こういうようなところは、今の我々が学ばなきゃならないところだと思うんです。日本はね、無縁社会って言われて、だんだん取りこぼされてしまう人が増えてきている。逆に日本のほうがね、ある意味では貧困であるって言えるかもしれない。
あとは、物を大切にするという意識がすごく強い社会システムになっている。例えば取っ手が取れてお鍋が壊れましたって言ったら、日本は捨てるじゃないですか。向こうの人はちゃんとお鍋の修理屋さんが来て、直してくれるんですよ。靴の修理屋さんもいて、サンダルの紐が切れれば直してくれるし、傘の修理屋さんもいて、傘の骨が折れれば直してくれる。それがすごく安く、5円とか10円とかで直してくれる。壊れても使い続けている。日本ってやろうと思えばできるけど、高いですよね、修理することが。
だから結局買ったほうが安いじゃんって言って買っちゃうんですけど、それでどんどんごみも増えるし、資源の無駄遣いにも繋がる。あと今回日本で震災の後の活動をしていて改めて思ったのは、例えばバングラデシュでは毎年洪水があるんです。水かさが上がって、家が水に浸かっちゃう。そうすると、また家建て直したりとかしなきゃならないんですけど、非常に復旧が早いですね。財産が日本みたいにいっぱい、家財道具とか電化製品なんかもほとんどないですから。そうするとお金もかからないですし、復旧もそんな時間がかからない。日本って全て失うと、それが元に戻るのはすごい大変なことじゃないですか。全て電化製品だからいちいち買い揃えないといけないし、家具もたくさん必要ですし、着るものも靴もたくさん必要。そうやって考えると、生きていくためのたくましさというか、生きる力というか、日本人は弱くなってんだろうなって思いました。
そういう学びっていうのはいろんな面でありますよね。よく言うんですけど、結局我々のほうがたくさん問題を抱えてるんじゃないかなって。我々が現地に行って、貧しいから大変で救ってあげなきゃって言っても、本当に向こうの人が自分たちが大変で助けてもらわなきゃいけないって思っているのかって怪しいですよね。本当に怪しいと思います。だから逆に日本のほうがやんなきゃいけないことがいっぱいあるんじゃないかなって気がするんです。我々の役割っていうのは、現地の人を助けるっていう部分もあるんだけれど、それよりも、そこから我々が学んで日本でどう活動を還元していけるのかっていうのが大きいのかなっていうことは思いますね。
学生にメッセージをよろしくお願いします。
若いうちにどんどん外に出てほしいなって。そこから見えてくるものっていうのは必ずあるはずなので。日本だけじゃなくって、日本以外のことにも関心を持つ人が増えていってほしいなって思います。それは海外協力に参加する人が増えてほしいっていうこともそうなんですけど、それだけじゃなくて、海外に目を向けることによって日本のことをより深く考えられるっていう側面もあると思うんです。日本のことを、日本だけしか知らない人が考えるよりも、ほかのいろんな世界の全体の状況の中で考えていったほうが、深くものをみられるときもあると思うんです。だから、どんどん外に出てほしいって、そう思いますね。
【参考】
ステナイ生活:シャプラニールが提案する、不要品を捨てずに国際協力へ活かす新しいライフスタイルです。シャプラニールへの寄贈品は、日本の専門業者で換金され、海外での支援活動に活かされます。誰でも参加できる、気軽な国際協力です。
詳しくはこちら。(http://www.shaplaneer.org/sutenai/index.php)
参加型農村開発手法(PRA手法): 発展途上国の農村において、現地の住民が自分たちの問題を自分たち自身で発見し、その解決に向けて参加する姿勢を養うためのさまざまな参加型学習の手法です。






